■ 最新記事
(08/15)
(08/14)
(08/13)
(08/12)
(08/11)
(08/10)
(08/09)
(08/08)
(08/07)
(08/06)
■ カテゴリー
お探し記事は【記事一覧 索引】が便利です。
■2010/03/09 (Tue)
シリーズアニメ■
1品目 ワグナリアへようこそ♪ 小鳥遊、働く。
住宅街の通りは雪に埋もれかけていた。雪を掻き分け、道の左右に高く積み上げてようやく灰色のアスファルトがちらと姿を現す。なのに、雪はなおも振り続けていた。空は灰色に沈み、絶え間なく振り続ける雪で風景は白く凍りかけていた。
小鳥遊宗太(たかなしそうた)は寒さに背中を丸めて、住宅街の通りを歩いていた。灰色のアスファルトは再び雪に覆われはじめ、泥を吸った足跡をいくつも刻んでいた。
宗太は、えっと振り返った。背中にもたれかかっていたのは、長い髪をポニーテールにしている小さな女の子だった。
「バイト……バイトしませんか!」
女の子は頬を赤くして、必死な表情で宗太に訴えた。
「大丈夫、親御さんは?」
きっと迷子の子だ。そう思って宗太は、女の子を屈みこんで穏やかな声で訊ねた。
今度は女の子がきょとんと考えるふうにした。
「えっと、お父さんは公務員で、お母さんは専業主婦です」
女の子は宣言でもするように、元気に手を上げた。
「え、そうじゃ……。ええっと、じゃあまずすぐそこの交番でも行こうか」
……かわいい。思わず宗太はしまりのない微笑を浮かべてしまった。でもとりあえず一般市民の
「あの、違います。ファミレスのバイト勧誘です。一緒に働きませんか」
女の子は一生懸命に首を左右に振って訂正しようとした。
「ええ? ああ、どうしよう。ファミレスごっこ? さすがにちょっと……」
女の子も困ったように首をぶんぶん振って、考えるようにうつむいた。
「違います。種島ポプラ17歳。高校生です!」
女の子――ポプラはばっとコートをはだけて、学生手帳を突きつけ
「ああ、高校生?」
宗太は信じられない気分でポプラを改めて見詰めた。
「ああ、それで、あの……バイトを探してくれる人
ポプラは不安そうになって、また大きな瞳をうるうるとさせた。
ポプラは寒そうに震えて、白く凍りつく息を吐いた。毛糸の手袋で口元を押える。白い頬を、ほんのりと赤く染めていた。それでもポプラは、必死な目でじっと宗太を見詰めていた。
かわいい……! 宗太はさっきより強く思った。しかし12歳以上でこの異様な可愛らしさはありなのだろうか。それにこの生徒手帳に制服、うちの高校と同じで、しかも僕の先輩だ。
「やります、バイト」
宗太は下心を悟られないように、落ち着いた微笑みを見せた。
「ほ、本当!」
ポプラが感激で目をきらきらさせた。
「はい」
宗太はポプラに頷きかける。
ガラス戸を押して入っていくと、奥にもう一つ自動扉がある。ピンポーンと来客を内部に告げる音がする。自動扉を潜っていくと、ぱたぱたと小さな女の子が飛び出してきて、私にお辞儀をした。
「いらっしゃいませ」
女の子に招待されたのは虚構世界の誰かではなく、この物語に接しているあなたである。あの境界を潜り、我々はワグナリアと呼ばれる異空間へと入っていくのだ。
多くの人が単に客としてその一部と接するだけのファミリーレストランだが、その内部世界となると、一般の人にとっては一種の異空間である。カウンターの裏に
物語の中心にあるのはユーモラスなキャ
レストランといえばパースの怪物で、アニメにおいては地味に作画困難なセットだ。だが『WORKING!!』はそんな苦労を
キャラクターの線は少ないが、一本一本に無駄を感じさせない。見る者にキャラク
『WORKING!!』はファミリーレストランの内部世界を描いた作品だが、あくまでもファミリーレストランは舞台でしかない。その場所で従
ファミリーレストランの内幕。そこは一般の人にとっては異界であり、映像のモチーフとしては新しい何かを提供する場所である。
WORKING!! 公式ホームページ
作品データ
監督・シリーズ構成:平池芳正 原作:高津カリノ
キャラクターデザイン・総作画監督:足立慎吾 プロップデザイン:明珍宇作
色彩設計:坂本いづみ 美術監督:田尻健一 編集:坪根健太郎
撮影監督:廣岡岳 音響監督:鶴岡陽太 音響制作:楽音舎 音楽:MONACA
プロデューサー:清水博之 斎藤朋之 斎藤俊輔
製作:「WORKING!!」製作委員会
制作:A-1 Pictures
出演:福山潤 阿澄佳奈 藤田咲 喜多村英梨
〇 渡辺久美子 小野大輔 神谷浩史 白石涼子
〇 日笠陽子 伊藤静 斉藤桃子
PR
■2010/02/06 (Sat)
劇場アニメ■
宗介は波間の漂流物の中に、小瓶に詰まった謎の生き物を拾
「金魚だ!」
いや、金魚ではないだろう。
ポニョは「魚の子」とされているが、どう頑張っても魚には見えな
だが宗介はポニョを見て「金魚だ」と断定し、その後ポニョは金魚、あるいは魚の子であるという前提で進行していく。
『崖の上のポニョ』は子供の視点が貫かれている。世界はまだド
あらゆる原理が絶対のものとして膠着している大人の視点で見ると、『崖の上のポニョ』はあまりにも渾沌として不可解なもののように映る。物語構造は破綻しているようにすら見えてしまう。
『崖の上のポニョ』は、世界は絶対のものであるという限界を飛び越え、驚くべきビジョンを描いた作品である。
そう願ったポニョは人間に姿を変えて、大津波と共に地上に飛び出してくる。大津波は港街を飲み込み海底に沈めてしまうと、宗介の乗る車を猛然と追跡してくる。
そうして街は水の底に沈んでしまうが、映画は一切悲劇的に描いていないし、通り過ぎる人々の顔にも不安や悲しみは一切見
おそらくは日本人的な自然への信頼感がそこにあるからだろう。日本人は自然の浄化能力を強く信じている。水没しても必ず
水没した街の風景も、渾沌とした破壊の印象はない。水中の色彩は瑞々しく輝き、水に沈む街は黄昏ではなく再生と浄化を連想させる。水没した街にはデボン紀の生物がレイヤリングされ、生命が新しい力を得た瞬間の活力をそこに描き出している。
未確認の情報だが、宮崎駿は『崖の上のポニョ』製作中に、フラ
フライシャー兄弟とは、1920年から40年ごろまで、短編を中心に多くの作品を制作したアニメーション作家である。1920
フライシャー兄弟の作品を見ると、まるで夢の世界に迷い込んだ心地になる。夢と言っても、「美しく幻想的な」という意味ではない。不可解で不安にさせるほうの夢だ。
宮崎駿が本当にフライシャー兄弟を参考にしたのかは不明だが、見比べてみると確かにフライシャー兄弟を思わせる場面が多く見られる。主人公のポニョからして謎の生物だし、魚と人間の中間にある第2形態はさらに不可解なものを強めている。目玉をつけた波が魚の形に変わったり、グランマンマーレは存在自体がアンビリーバボーだ。やはり感情的な動きが通俗的原理より優先して描かれ、ポニョの感情の動きに釣られて大津波が引き起こされてしまうし、その後の水没した街に対して誰も不思議を感じていない。
単にアニメーションそのものへの根源に回帰したとも言えるが、確かにフライシャー的な場面があちこちに見られるようである。
発端は、元サイゾー記者をジブリに受け入れたことに始まっている。その記者は恋人に振られたショックで仕事を辞め、アメリ
それを知らずに鈴木敏夫は「じゃあジブリに来たら?」とこの記者を誘った。
「ジブリに入れるんなら」とこの記者はアメリカ行きをキャンセル
ところがその後もこの記者は働いている気配を見せない。
「あいつどうしてるの?」
「さあ?」
(資料:CUT2008年3月号)
宮崎駿にとって、映画の文法とは高畑勲であった。宮崎駿は高
宮崎駿に変化が現れてきたのはおそらく『千と千尋の神隠し』で
『崖の上のポニョ』において、ついに高畑勲の呪縛から解放され
『崖の上のポニョ』は他のどの作品とも似ていない驚くべきオリジナル作
『崖の上のポニョ』はまるで生まれたばかりの
『千と千尋の神隠し』と『ハウルの動く城』に描かれた死のイメージの向うにあったのは、意外にも生命誕生のビジョンである。『崖の上のポニョ』は原始の時代のように、新しい生命の輝きに満たされている。
作品データ
監督・原作・絵コンテ:宮崎駿
作画監督:近藤勝也 作画監督補:高坂希太郎、賀川愛、稲村武志、山下明彦
美術監督:吉田昇 美術監督補:田中直哉、春日井直美、大森崇
色彩設計:保田道世 映像演出:奥井敦 編集:瀬山武司
音楽:久石譲 音響効果:笠松広司 整音:井上秀司
主題歌:
『海のおかあさん』
作詞:覚和歌子 宮崎駿(覚和歌子「さかな」より翻案) 作曲・編曲:久石譲 歌:林正子
『崖の上のポニョ』(ヤマハミュージックコミュニケーションズ)
作詞:近藤勝也 補作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 歌:藤岡藤巻と大橋のぞみ
制作:星野康二 プロデューサー:鈴木敏夫
アニメーション制作:スタジオジブリ
出演:奈良柚莉愛 土井洋輝 山口智子 長嶋一茂
〇 所ジョージ 天海祐希 矢野顕子 吉行和子
〇 奈良岡朋子 左時枝 平岡映美 大橋のぞみ
■2010/01/26 (Tue)
映画:外国映画■
誰もが人に聞いた。
「タイラー・ダーデンを知っているか?」

僕は半年間、不眠症に悩まされていた。眠れない日々が続くと現実の何もかもが曖昧になる。遠くにかすんで、コピーのコピーのコピーのように擦り切れてしまう。
「不眠症では死なないよ」
医者は突き放すように診断を下した。 薬も出してくれない。頼むよ、苦しんだ。
薬も出してくれない。頼むよ、苦しんだ。
「君が苦しい? 睾丸ガン患者のグループに出てみろよ。あれが本当の苦しみだ」
僕は睾丸がん患者のグループセラピーに参加した。そこで出会ったのがボブ。
 ボブはボディビルの元チャンピオンだったが、筋肉増強剤の濫用でホルモンバランスが崩壊し、今や神の乳房を持つ大男になっていた。
ボブはボディビルの元チャンピオンだったが、筋肉増強剤の濫用でホルモンバランスが崩壊し、今や神の乳房を持つ大男になっていた。
見知らぬ他人の告白は僕の心を揺さぶった。自分でも思いがけず堰が崩れて、涙が出た。沈黙と忘却の暗黒に身を投じて、自由になる心地を見出した。
僕は眠れるようになった。
それが切っ掛けで、僕は毎日あらゆるグループセラピーに参加した。
アルコール依存症、過食症、脳神経症……。
僕はガンでもなければ死に掛けてもいなかった。この連中が取り囲む世界の、小さな中心だった。僕は毎晩彼らと一緒になって死を見つけ、その度に再生した。蝶が脱皮して背伸びをしている感じだ。マスターベーションより遥かに心地のいい解放感だった。
 そんな夢心地をあの女がぶち壊しにした。
そんな夢心地をあの女がぶち壊しにした。
「ここ、睾丸ガン患者のグループでしょ?」
やってきたのはマーラ・シンガー。
女が睾丸ガン患者? とんだイカサマ女だ。どこも悪くなかった。
 マーラは血液感染症の会にも顔を出していた。隔月の異常赤血球症患者の会にも。金曜の結核患者の会にも出席していた。
マーラは血液感染症の会にも顔を出していた。隔月の異常赤血球症患者の会にも。金曜の結核患者の会にも出席していた。
マーラ……観光気分の見物人。
「あなたも同じよ。インチキ」そう言われたような気がして、僕は泣けなくなり、再び不眠症になった。
 飛行機では何もかも1回分だ。1回分のパックの旅。砂糖もミルクも1回分。バターも1回分。おままごとのような機内食。1回分のシャンプー液。
飛行機では何もかも1回分だ。1回分のパックの旅。砂糖もミルクも1回分。バターも1回分。おままごとのような機内食。1回分のシャンプー液。
機内で隣り合わせる人は1回分の友達だ。タイラー・ダーデンはそん な1回分の友達の1人だった。
な1回分の友達の1人だった。
「知ってるか? ガソリンと冷凍オレンジジュースでナパーム弾が作れる。家庭にあるどんなものでも爆弾が作れる。本気だしゃあね」
タイラーは1回分の友達の中で最高の男だった。

タイラー・ダーデンとの出会いは僕を劇的に変えた。いや僕だけではなく、僕たち皆を変えた。タイラーは男達が喉元で引っ掛かっていたものを引っ張り出したんだ。
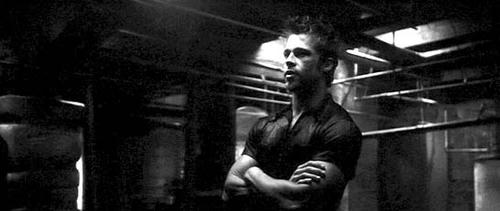 タイラーは男たちを集めて「ファイト・クラブ」を作った。それは僕から皆へのプレゼントだった。
タイラーは男たちを集めて「ファイト・クラブ」を作った。それは僕から皆へのプレゼントだった。
「諸君。ファイト・クラブへようこそ。
ファイト・クラブルールその1。ファイト・クラブのことは口にするな。
ファイト・クラブルールその2。絶対にファイト・クラブのことは口にするな。
ファイト・クラブルールその3。降参を告げたり、大怪我や戦意喪失はそこでファイト終了。
ファイト・クラブルールその4。1対1で戦う。
ファイト・クラブルールその5。1組ずつやる。
ファイト・クラブルールその6。シャツと靴は脱げ。
ファイト・クラブルールその7。決着がつくまでファイトをやめることはできない。
ファイト・クラブルールその8。初めてこのクラブに来た者は必ず戦え」
 『ファイト・クラブ』はコロンバイン高校銃乱射事件の後、最初に公開されたバイオレンス映画だった。まだ社会がヒステリックにざわついている最中で、『ファイト・クラブ』は格好の槍玉に挙げられた。批評家からはボロ糞の評価が下され、興行的には惨敗。製作を決行した会社役員が何人も更迭された。
『ファイト・クラブ』はコロンバイン高校銃乱射事件の後、最初に公開されたバイオレンス映画だった。まだ社会がヒステリックにざわついている最中で、『ファイト・クラブ』は格好の槍玉に挙げられた。批評家からはボロ糞の評価が下され、興行的には惨敗。製作を決行した会社役員が何人も更迭された。
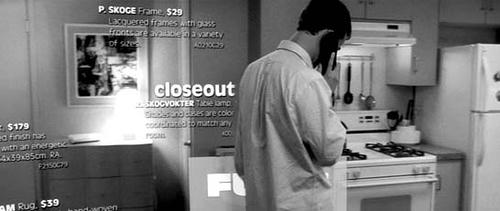 現代は広告が人間を形成している。広告媒体であるメディアが人間を作り、その人間が社会を作る。現代におけるイデアの神はメディアである。
現代は広告が人間を形成している。広告媒体であるメディアが人間を作り、その人間が社会を作る。現代におけるイデアの神はメディアである。
俺たちは何を考えるべきであるのか、ある対象に対してどう感じるべ きなのか。好意を抱くべきか嫌悪をするべきなのか。その判断のすべてを、俺たちはメディアに委ねて、自身で思考する努力を怠っている。
きなのか。好意を抱くべきか嫌悪をするべきなのか。その判断のすべてを、俺たちはメディアに委ねて、自身で思考する努力を怠っている。
俺たちは広告業界というお釈迦様の掌で踊らされいるだけの間抜け な猿だ。
な猿だ。
それはお前自身の考えか?
お前自身の言葉はどこにある?
目を見開いてそこにある現実を見ろ。人間自身を見ろ。俺は俺だ! お前が見ているのは広告業界の作り出した幻影だ。
お前が見ているのは広告業界の作り出した幻影だ。
 『ファイト・クラブ』が社会的な影響から逃れ、純粋に作品が評価されるまで数年の時間が必要だった。今では各映画誌で集計する“映画史上の名作ランキン
『ファイト・クラブ』が社会的な影響から逃れ、純粋に作品が評価されるまで数年の時間が必要だった。今では各映画誌で集計する“映画史上の名作ランキン グ”などに必ず20位以内に選出される。
グ”などに必ず20位以内に選出される。
現代人は広告業界が分類したカテゴライズを受け入れてしまっている。現代人は人間を見て人間を見ていない。現代人が見ているのは“何系”と集約されたカテゴライズであって、人間自身ではない。
 自分は“何系”の人間であるのか。自分がどの括りに属する人種なのか絶えず注意を払い、その属性が社会での自分の立場を決定してくれると信頼している。
自分は“何系”の人間であるのか。自分がどの括りに属する人種なのか絶えず注意を払い、その属性が社会での自分の立場を決定してくれると信頼している。
現代人の実体は、中身のない抜け殻だ。それをごまかすように、広 告会社が宣伝する装飾でアバター(仮人格)を飾り立てている。お前たちは広告会社の作り出したイミテーションであって、コピーを繰り返して象のぼやけた影に過ぎない。
告会社が宣伝する装飾でアバター(仮人格)を飾り立てている。お前たちは広告会社の作り出したイミテーションであって、コピーを繰り返して象のぼやけた影に過ぎない。
現代人はヒューマニズムの力を失っている。個人としての力など誰も 求めていない。ただ社会を機能させるための成員であることだけが求められ、その人間が誰であるかなど誰も求めていない。もっといえば、お前などいなくても社会は何の問題もなく機能するのだ。今や人間が社会を動かしているのではなく、社会が人間を奴隷にしている
求めていない。ただ社会を機能させるための成員であることだけが求められ、その人間が誰であるかなど誰も求めていない。もっといえば、お前などいなくても社会は何の問題もなく機能するのだ。今や人間が社会を動かしているのではなく、社会が人間を奴隷にしている のだ。
のだ。
 日本ではブラッド・ピット主演のアイドル映画として売り出された。「ブラピかっこいー! サイコー!」と。宣伝とかけ離れた暴力映画であると知って観客は驚い
日本ではブラッド・ピット主演のアイドル映画として売り出された。「ブラピかっこいー! サイコー!」と。宣伝とかけ離れた暴力映画であると知って観客は驚い ただろう。もちろん日本での興行は惨敗だった。
ただろう。もちろん日本での興行は惨敗だった。
現代人の孤独は社会が積極的に作り出したものだ。社会が集団を細かなカテゴライズで分断させ、その内部に格差と不和を作り出し、連帯の力を弱めた。広告会社が戯れに作った言葉を社会に浸透さ せ、自分たちの影響力を誇示するためだ。
せ、自分たちの影響力を誇示するためだ。
結果として人間は人間ではなく、カテゴライズという一集団でその対象を見るようになった。同じ国籍の人間だが違う人種だ。それがいつの間にかセックスする相手もいない孤独を作り出した。
 現代人は人間の社会の中で漂流する、宿命的な異民族である。しかもそこに、中心となる社会がない――いや、中心と思われていた社会はあったのだが、その地位を失いつつある。
現代人は人間の社会の中で漂流する、宿命的な異民族である。しかもそこに、中心となる社会がない――いや、中心と思われていた社会はあったのだが、その地位を失いつつある。
『ファイト・クラブ』はそんな現代社会の閉塞感に対して強烈なルサン チマンを叩きつける。俺は俺だ。広告会社の作り出した格差ではなく、己の拳で己自身を叩きつける。会社では何の役に立たない“立場”である平社員が、ファイト・クラブでは上司を叩きのめしている。それがファイト・クラブの魅力だ。
チマンを叩きつける。俺は俺だ。広告会社の作り出した格差ではなく、己の拳で己自身を叩きつける。会社では何の役に立たない“立場”である平社員が、ファイト・クラブでは上司を叩きのめしている。それがファイト・クラブの魅力だ。
 映画中にはしばしばタイラー・ダーデンがサブミニナルで映し出される。エドワード・ノートンが夢想したり、場面を嘲笑している瞬間などに現れる。ところで睾丸ガン患者グループのシーン、背景にアメリカ国旗が飾られている。「これが今のアメリカ」というわけなのだろうか。
映画中にはしばしばタイラー・ダーデンがサブミニナルで映し出される。エドワード・ノートンが夢想したり、場面を嘲笑している瞬間などに現れる。ところで睾丸ガン患者グループのシーン、背景にアメリカ国旗が飾られている。「これが今のアメリカ」というわけなのだろうか。
 タイラー・ダーデンは過剰に誇張された父性だ。過剰であるからこそ、タイラーはシンボリックな存在として、カリスマ的な崇拝すべき対象となった。
タイラー・ダーデンは過剰に誇張された父性だ。過剰であるからこそ、タイラーはシンボリックな存在として、カリスマ的な崇拝すべき対象となった。
カリスマは人々に言葉を与え、扇動し、新たな社会を作り出す。それ がいつの間にか支配と被支配という組織社会を作り出すようになる。
がいつの間にか支配と被支配という組織社会を作り出すようになる。
タイラー・ダーデンは男性性のシンボルとして男達から解放を与えた。その次の段階として破壊のシンボルへと移行した。より過剰な力で、社会を再創造しようと目論んだのだ。
 父性は解放を促すイコンではなくなり、単に支配するだけの存在に変わる。
父性は解放を促すイコンではなくなり、単に支配するだけの存在に変わる。
 お前は自分以外の全てがクソだと思ってやがる。はっきり言ってやる。そのクソはお前の尻から出た物
お前は自分以外の全てがクソだと思ってやがる。はっきり言ってやる。そのクソはお前の尻から出た物 だ。もっと言ってやる。そのクソはお前自身だ。広告が作り出したまやかしの幻覚に逃れるな。お前はい
だ。もっと言ってやる。そのクソはお前自身だ。広告が作り出したまやかしの幻覚に逃れるな。お前はい つから何も感じないジジイみたいに萎えちまったんだ。殴り合ってみろ。狂気を呼び覚ませ。苦痛を取り
つから何も感じないジジイみたいに萎えちまったんだ。殴り合ってみろ。狂気を呼び覚ませ。苦痛を取り 去るな。不愉快から目を逸らして逃げるな。世界のすべてを受け入れ、自分の足で歩け。
去るな。不愉快から目を逸らして逃げるな。世界のすべてを受け入れ、自分の足で歩け。
文化とは芸術が劣化し大衆化した姿だ。人間はその文化を模倣して、それを足がかりに生活し、行動規範を決めている。
 『ファイト・クラブ』の公開後、多くの人が懸念したのは『ファイト・クラブ』そのものを模倣することだった。コロバイン高校銃撃事件の直後という時期もあり、人々は『ファイト・クラブ』を警戒した。当時、人々はコロンバイン事件の真相を人間の心理や社会に求めず、誰もが何かの
『ファイト・クラブ』の公開後、多くの人が懸念したのは『ファイト・クラブ』そのものを模倣することだった。コロバイン高校銃撃事件の直後という時期もあり、人々は『ファイト・クラブ』を警戒した。当時、人々はコロンバイン事件の真相を人間の心理や社会に求めず、誰もが何かの ――例えば映画やテレビゲームの影響であると信じようとしていた。社会は安易な答えで安心を得ようとしていた。
――例えば映画やテレビゲームの影響であると信じようとしていた。社会は安易な答えで安心を得ようとしていた。
だが考えてみれば『ファイト・クラブ』はコインの裏と表のような存在だ。コインの表とは即ち広告会社が作り出したアジテーションだ。 『ファイト・クラブ』が語ってみせたのは、もはや空気のようになって存在すら感じられず、しかし確実に我々の生活からモラル、美意識にまで影響を与え、操作している広告会社の存在についてだ。『ファイト・クラブ』は人間が擦り切れのコピーになっている現実を指弾し、ニー
『ファイト・クラブ』が語ってみせたのは、もはや空気のようになって存在すら感じられず、しかし確実に我々の生活からモラル、美意識にまで影響を与え、操作している広告会社の存在についてだ。『ファイト・クラブ』は人間が擦り切れのコピーになっている現実を指弾し、ニー チェ的な力の回復を促している。
チェ的な力の回復を促している。
『ファイト・クラブ』は見る者の心理に語りかけ、行動を引き起こさせる強引な力がある。それが見る人によっては凄まじい嫌悪感を呼び起こすのだろう。称賛する人がいる一方、拒絶する人も多かった。
 それこそ、その状況こそ『ファイト・クラブ』が目論んでいるテーマだ。“動揺”を与えるために作られた映画だからだ。
それこそ、その状況こそ『ファイト・クラブ』が目論んでいるテーマだ。“動揺”を与えるために作られた映画だからだ。
 『ファイト・クラブ』は甘い揺り篭に守られている現代人を目覚めさせ、顔を掴んで無理やり振り向かせようとしている。そこに何が見えるのか? そこで見えたものがこの映画の答えだ。
『ファイト・クラブ』は甘い揺り篭に守られている現代人を目覚めさせ、顔を掴んで無理やり振り向かせようとしている。そこに何が見えるのか? そこで見えたものがこの映画の答えだ。
映画記事一覧
作品データ
監督:デヴィッド・フィンチャー 原作:チャック・パラニューク
音楽:ザ・ダスト・ブラザーズ 脚本:ジム・ウールス
撮影監督:ジェフ・クローネンウェス 衣装:マイケル・カプラン
編集:ジェームズ・ヘイグッド 特殊メイク:ロブ・ボッティン
出演:エドワード・ノートン ブラッド・ピット
〇 ヘレナ・ボナム=カーター ミート・ローフ・アディ
〇 ジャレッド・レトー ザック・グルニエ
〇 ピーター・イアカンジェロ デヴィッド・アンドリュース
〇 リッチモンド・アークエット アイオン・ベイリー
「タイラー・ダーデンを知っているか?」
僕は半年間、不眠症に悩まされていた。眠れない日々が続くと現実の何もかもが曖昧になる。遠くにかすんで、コピーのコピーのコピーのように擦り切れてしまう。
「不眠症では死なないよ」
医者は突き放すように診断を下した。
「君が苦しい? 睾丸ガン患者のグループに出てみろよ。あれが本当の苦しみだ」
僕は睾丸がん患者のグループセラピーに参加した。そこで出会ったのがボブ。
見知らぬ他人の告白は僕の心を揺さぶった。自分でも思いがけず堰が崩れて、涙が出た。沈黙と忘却の暗黒に身を投じて、自由になる心地を見出した。
僕は眠れるようになった。
それが切っ掛けで、僕は毎日あらゆるグループセラピーに参加した。
アルコール依存症、過食症、脳神経症……。
僕はガンでもなければ死に掛けてもいなかった。この連中が取り囲む世界の、小さな中心だった。僕は毎晩彼らと一緒になって死を見つけ、その度に再生した。蝶が脱皮して背伸びをしている感じだ。マスターベーションより遥かに心地のいい解放感だった。
「ここ、睾丸ガン患者のグループでしょ?」
やってきたのはマーラ・シンガー。
女が睾丸ガン患者? とんだイカサマ女だ。どこも悪くなかった。
マーラ……観光気分の見物人。
「あなたも同じよ。インチキ」そう言われたような気がして、僕は泣けなくなり、再び不眠症になった。
機内で隣り合わせる人は1回分の友達だ。タイラー・ダーデンはそん
「知ってるか? ガソリンと冷凍オレンジジュースでナパーム弾が作れる。家庭にあるどんなものでも爆弾が作れる。本気だしゃあね」
タイラーは1回分の友達の中で最高の男だった。
タイラー・ダーデンとの出会いは僕を劇的に変えた。いや僕だけではなく、僕たち皆を変えた。タイラーは男達が喉元で引っ掛かっていたものを引っ張り出したんだ。
「諸君。ファイト・クラブへようこそ。
ファイト・クラブルールその1。ファイト・クラブのことは口にするな。
ファイト・クラブルールその2。絶対にファイト・クラブのことは口にするな。
ファイト・クラブルールその3。降参を告げたり、大怪我や戦意喪失はそこでファイト終了。
ファイト・クラブルールその4。1対1で戦う。
ファイト・クラブルールその5。1組ずつやる。
ファイト・クラブルールその6。シャツと靴は脱げ。
ファイト・クラブルールその7。決着がつくまでファイトをやめることはできない。
ファイト・クラブルールその8。初めてこのクラブに来た者は必ず戦え」
俺たちは何を考えるべきであるのか、ある対象に対してどう感じるべ
俺たちは広告業界というお釈迦様の掌で踊らされいるだけの間抜け
それはお前自身の考えか?
お前自身の言葉はどこにある?
目を見開いてそこにある現実を見ろ。人間自身を見ろ。俺は俺だ!
現代人は広告業界が分類したカテゴライズを受け入れてしまっている。現代人は人間を見て人間を見ていない。現代人が見ているのは“何系”と集約されたカテゴライズであって、人間自身ではない。
現代人の実体は、中身のない抜け殻だ。それをごまかすように、広
現代人はヒューマニズムの力を失っている。個人としての力など誰も
現代人の孤独は社会が積極的に作り出したものだ。社会が集団を細かなカテゴライズで分断させ、その内部に格差と不和を作り出し、連帯の力を弱めた。広告会社が戯れに作った言葉を社会に浸透さ
結果として人間は人間ではなく、カテゴライズという一集団でその対象を見るようになった。同じ国籍の人間だが違う人種だ。それがいつの間にかセックスする相手もいない孤独を作り出した。
『ファイト・クラブ』はそんな現代社会の閉塞感に対して強烈なルサン
カリスマは人々に言葉を与え、扇動し、新たな社会を作り出す。それ
タイラー・ダーデンは男性性のシンボルとして男達から解放を与えた。その次の段階として破壊のシンボルへと移行した。より過剰な力で、社会を再創造しようと目論んだのだ。
文化とは芸術が劣化し大衆化した姿だ。人間はその文化を模倣して、それを足がかりに生活し、行動規範を決めている。
だが考えてみれば『ファイト・クラブ』はコインの裏と表のような存在だ。コインの表とは即ち広告会社が作り出したアジテーションだ。
『ファイト・クラブ』は見る者の心理に語りかけ、行動を引き起こさせる強引な力がある。それが見る人によっては凄まじい嫌悪感を呼び起こすのだろう。称賛する人がいる一方、拒絶する人も多かった。
映画記事一覧
作品データ
監督:デヴィッド・フィンチャー 原作:チャック・パラニューク
音楽:ザ・ダスト・ブラザーズ 脚本:ジム・ウールス
撮影監督:ジェフ・クローネンウェス 衣装:マイケル・カプラン
編集:ジェームズ・ヘイグッド 特殊メイク:ロブ・ボッティン
出演:エドワード・ノートン ブラッド・ピット
〇 ヘレナ・ボナム=カーター ミート・ローフ・アディ
〇 ジャレッド・レトー ザック・グルニエ
〇 ピーター・イアカンジェロ デヴィッド・アンドリュース
〇 リッチモンド・アークエット アイオン・ベイリー
■2010/01/24 (Sun)
映画:外国映画■
第3章 王の帰還
THE RETURN OF THE KING
THE RETURN OF THE KING
ゴラムは以前、スメアゴルと呼ばれるホビットであった。アンドゥインのほとりに住むホビット三支族の1つである、ストゥア族の生まれであった。
ゴラムに悲劇が訪れたのは不運によるものであった。
その日、スメアゴルは友人のデアゴルと釣りに出かけていた。小さな小舟に乗り、のどかに釣り糸を垂らしていた。間もなくデアゴルの釣り針に魚が食いついた。デアゴルは引き上げようとしたが魚は大きく、デアゴルを水中に引きこんでしまった。
間もなくデアゴルは岸に這い上がるが、その頭に水草を絡め、手には一掴みの泥が握られていた。その泥に、金色に輝く指輪が混じっていた。
「デアゴル。それを俺にくれないか? 俺の誕生日だろう?」
ストゥア族の者たちはスメアゴルを「人殺し」罵り、石を投げて里から追放した。スメアゴルは古里を遠く離れ、霜降り山脈を住処にした。
いつしかスメアゴルは、自身の名前も忘れ、ただただ指輪に取り憑かれるだけのおぞましい生き物になってしまった。
「何て奴らだ! あちこち探してみたのに、見つけてみりゃ腹いっぱい食い、パイプ草!」
アイゼンガルドの戦いもちょうど終ったところだった。エントたちの怒りの襲撃によってアイゼンガルドの施設は崩壊し、忌まわしき地下の溶鉱炉もダム決壊の濁流によって洗い流された後であった。ウルク=ハイの軍団ももはや1人も残っていなかった。アイゼンガルドに残されていたのはオルサンクに篭城するサルマンただ1人だけだった。
ガンダルフはオルサンクの前に進み、サルマンと話し合いを始めた。サルマンは哀れな老人の振りをしてセオデンを誘いかけるが、セオデンはサルマンの魔術を察して断固拒否。
グリマに反抗心が浮かび、サルマンに飛び掛って背中からナイフを突き立てた。そのグリマをレゴラスが矢で射抜く。絶命したサルマンはオルサンクの塔から落ちて絶命した。
ローハンの男達は戦いを終えて祝杯を上げていた。だがサウロンとの戦いはまだ終わってないし、次にどんな手を討ってくるのか想像もできない。それにフロドの生死も不明だった。無事にモルドールに向っているのか、手掛かりは何もなかった。
アラゴルンとガンダルフが助けに入ってピピンからパランティアを引き離した。ピピンは悪しき魔力に消耗していたが、パランティアから白い木のイメージを読み取っていた。
白い木――それはミナス・ティリスに置かれているイシリアンの木だ。ゴンドールに再び王が戻るその時、花を咲かせると呼ばれる木だ。
サウロンの次なる手が判明した。サウロンはゴンドールの首都ミナス・ティリスを襲うつもりだ。ゴンドール王が帰還する前にその玉座を破壊する計画だ。
ガンダルフはピピンを連れて飛蔭に跨った。サウロンはピピンが指輪を持っていると思っている。だからあえてピピンを連れてゴンドールへ向うのだ。
ペレンノール野に暗雲が覆いつつあった。あれは自然の風が送り込んでくる雲ではない。陽の光を嫌うオークの軍団を送り込むために、サウロンが作り出した雲だ。
間もなくオスギリアスを守備していたファラミアが、襲撃を受けてミナス・ティリスに遁走してきた。サウロンの闇の軍勢はオスギリアスの防衛線を乗り越えて次々と押し寄せようとしている。戦いの時が今まさに訪れようとしていた。
フロドたちはオークの軍団に見つからないように身を潜め、ゴラムの案内で崖に刻まれた長い階段を登って行く。
フロドはゴラムとともに階段を登りきり、その先のトンネルに入り込
ようやく駆けつけたサムがシェロブを撃退するが、すでにフロドは息を
とそこで、サムはオークたちの会話で、フロドは仮死状態になっただけで死んでいないと知る。しかしフロドはオークたちが根城にする塔に従れさらわれてしまった。
最終章だが物語が小さくつづまっていく感じはない。これまで以上に複雑で雄大かつ壮絶な戦いの物語が繰り広げられ、英雄
映画の背景においてもはや解説の必要がなく、ドラマを語るべき段階に入ったからだ。だからこそ第3部は、シリーズにおいて
第3部に入って、登場人物たちはそれぞれに試練が与えられる。狂気に捉われたデネソールから父としての愛を得ようとする
その中でもとりわけ存在感を放つのがさすらいのレンジャー・アラゴルンだろう。アラゴルンは指輪に捉われて殺されたイシルドゥアの末裔にして正当なる後継者である。だがそれだけに、自身の弱さを恐れている。かつてイシルドゥアが犯した過ちを自分も犯すのではないか――その血を引いている限り、指輪に捉われた王という宿命から逃れられないのではないか。
だからアラゴルンは身分を隠し、野伏として生きてきた。それはサウロンたちの勢力から身を隠すためでもある。
だが第3部において、ついにアラゴルンは自らの宿命を受け入れて戦いの覚悟を決める。王の剣であるナルシルが鍛えなおされ、アンドゥリルの剣として復活した。アラゴルンはイシルドゥアの後継者として王の剣を持ち、かつて王に忠誠を誓った軍団を束ねていく。
それからのアラゴルンの活躍、勇猛さは映画をご覧のとおりだ。アラゴルンを演じたヴィゴ・モーテンセンは王の風格と聡明さを見事に体現している。ヴィゴ・モーテンセンなら王として君臨しても相応しいという気にさせてくれる。
第3部においてもっと感動的なドラマを演じてみせたのは、間違いなくフロドたちであろう。指輪の魔力で衰弱し、それでも諦め
第3部はどこまでも厳しくつらい試練の場面である。誰もがぎりぎりの戦いに挑戦し、その苦しみに対し、恐れは抱くものの決し
映画『ロード・オブ・ザ・リング』において素晴らしい成長を遂げたのは映画内におけるキャラクター達だけではない。映画製作会社WETAは今や映画産業においてなくてはならない制作会社になった。
もともとは『ロード・オブ・ザ・リング』の制作のためだけに作られた制作スタジオだったが、今やその枠をとっくに超えてしまっている。当初は専門学校をちょっと出たばかりの学生ばかりが集る頼りなげな制作会社だったが、映画が終わる頃には世界中が認める一流企業になった。
最近制作された規模の大きな映画はほぼすべてWETAが関わっているといっていいくらいだ。WETAの個性はデジタル技術だけではなく(デジタルばかり注目されるが)、あらゆる物もなければ作ってしまえ、という心構えにある。衣装やプロップといったものを、紛い物ではなく本物を作ってしまう技術と職人を抱えているのだ。緻密に作られた装飾品や、鍛冶職人が鍛え上げた本物のようではなく、紛れもなく本物の鎧や剣。そうした本物を作れる職人がいるのもWETAの魅力でもある。
総制作費340億円という大きな予算も第1作目で全て回収し、第2部はそれ以上の利益を上げてしまった『ロード・オブ・ザ・リング』である。もはや世界中の誰もが待ち望む作品の1つであった。それだけに、待ちに待った第3部の熱狂はすさまじいものであった。
日本におけるワールド・プレミアは増上寺で開催された。東京タワーをバラド=ドゥアに見立てて、魔法の指輪を本殿に奉納するという式典であった。
日本のワールド・プレミアも相当金のかけた大掛かりなものであったが、本国ニュージーランドはもっと際立っていた。
ウェリントンの国会議事堂をスタート地点としておよそ3キロに及ぶレッドカーペットが敷かれ、出演者達がオープンカーに乗ってパレードをするのである。レッドカーペットの周囲にはニュージーランド中から人々が押し寄せて、大興奮で出演者達を迎え入れた。そんなパレードが始まると、空中をフロドたちの写真をプリントされた旅客機が旋回するのである。
まさに偉大なる戦いを勝利した英雄を歓迎する行進であった。
「すると見よ! 盾は太陽の化身さながらに燦然と輝き、乗馬の白い足の駆けるとこ
なんと“暗闇は取り除かれる”以外は記述通りそのままだ。監督がこの記述からどのようなイメージを持ち、どう発展させていったか。『キング・コング』の事例でもそうであったが、ピーター・ジャクソンのイマジナリティを読み解く1つのヒントになりそうだ。
《イントゥ・ザ・ウエスト》は過酷な旅に疲れた者の心を癒し、安ら
だがこの歌の中心人物はフロドやアラゴルンとは別にもう1人い
ピーター・ジャクソンは妻のフラン・ウォルシュとともに臓器提供
だがコンタクトを取ってみるとキャメロン・ダンカンはすでにガン
それでもキャメロン・ダンカンは死に怯えず映画製作に打ち込んだ。自身を主役に据えて、自身の痕跡を残すために映画を作り、短編映画『ストライク・ゾーン』を完成させたと同時に死亡した。
同じ頃、フラン・ウォルシュは《イントゥ・ザ・ウエスト》の作詞の最中であったが、この事件が作詞に大きな影響を与えた。《イントゥ・ザ・ウエスト》の歌詞が示している安らぎと祝福の対象はもちろんフロドたちであるが、もう1人キャメロン・ダンカンに向けられているのだ。
アカデミー賞11部門ノミネート、その全てにおいて受賞。これは
だがそんな映画にもお別れのときがやって来た。その最後は最
闇の世界から放たれた大波は、緑の野と山々を飲み込み、何
希望がどこにも見えない物語。しかしそれでも私たちの心を離さず、強く捕らえて進んでいく。
そんな物語の最後には英雄が平和を獲得する。古里に帰っていくと、古い友人たちが旅立った者を受け入れ、途切れていた時間などなかったかのように日常が回りだす。
だが一度平和の里を出てしまった者にとって、途切れてしまった日常は元に戻せない。
こうして物語は閉じていく。創作の世界が我々の前に扉を開けるのはほんの僅かな時でしかない。夢の世界の住人と共にできるのは束の間でしかない。あのどこまでも広がる野も、白く輝く浜も、静かな空を舞う鳥たちも、潤いの雨を降らす雲も、物語の終わりと同時に我々の前から去っていく。
さあおしまいだ。
だが誰にとっても『ロード・オブ・ザ・リング』の物語は離れがたいものであった。読者の全てが通過したように、出演者や製作スタッフたちも別れを惜しんだ。出演者や製作スタッフにとって、単純な別れではなかった。もはや人生の一部になりかけていた創作物である。
もっと掘り下げる余地があるかもしれない。もっと精度を上げられるかもしれない。何よりも離れがたい。
だが別れの時はやってきた。映画の完成と共に、人々は永遠の友情と愛を誓い合い――解散した。
第1章『旅の仲間』を読む
第2章『2つの塔』を読む
映画記事一覧
作品データ
監督:ピーター・ジャクソン 原作:J・R・R・トールキン
脚本:フラン・ウォルシュ フィリパ・ボウエン
コンセプチュアルデザイナー:アラン・リー ジョン・ハウ
音楽:ハワード・ショア 主題歌:アニー・レノックス
撮影:アンドリュー・レスニー 編集:ジョン・ギリバート
衣裳:ナイラ・ディクソン リチャード・テイラー
出演:イライジャ・ウッド イアン・マッケラン
〇 ヴィゴ・モーテンセン ショーン・アスティン
〇 ビリー・ボイド ドミニク・モナハン
〇 オーランド・ブルーム ジョン・リス=デイヴィス
〇 ショーン・ビーン アンディ・サーキス
〇 ケイト・ブランシェット リヴ・タイラー
〇 マートン・ソーカス イアン・ホルム
〇 バーナード・ヒル ミランダ・オットー
〇 カール・アーバン デヴィッド・ウェンハム
〇 ブラッド・ドゥーリフ クリストファー・リー
〇 ジョン・ノーブル
■2010/01/22 (Fri)
映画:外国映画■
第2章 2つの塔
THE TWO TOWERS
THE TWO TOWERS
メリーとピピンの2人がフロドと間違えられて
アラゴルンを筆頭にレゴラス、ギムリの3人が徒党を組んでラウロスの滝を去ったウルク=ハイ追跡を始めた。だが相手は疲れ知らずのウルク=ハイたちだ。追跡は休憩も食事もなしで幾日も続いた。
その途上でアラゴルンはウルク=ハイたちが踏み散らかした足跡に紛れるようにロリアンのブローチが落ちているのに気付く。メリーかピピンか、自分たちが追跡しているのを察して目印を残したのだ。
ウルク=ハイたちはローハン草原を横切って西へ、サルマンの待つアイゼンガルドに向うつもりだ。アラゴルンたちは休みなしの決死の強行軍を続けた。
「ローハンの騎士たちよ、何があった!」
メリーとピピンは彼らの殺されたのか。アラゴルンたちは愕然と、行く手に吹き上がる黒い煙に目を向けた。
だがエオメルは単独で自分の部下達を引き連れ、ローハンを蹂躙する魔の軍勢を討伐する旅を続けていた。
アラゴルンたちはエオメルと分れてウルク=ハイの死体が積みあがる場所へ向った。確かにそこにメリーピピンの姿はなかった。
だがアラゴルンは争いの痕跡の中に小さな足跡を見つける。ここを這ったんだ。ここでロープを千切って立ち上がった。足跡はさらに続き、その向うのファンゴルンの鬱蒼とした森の中へと続いていた。
メリーとピピンは生きている。アラゴルンは森の中へ入っていき、その行方を探した。
ガンダルフの戦いは谷底への落下中から始まっていた。剣を手
同時にガンダルフも力尽きて倒れた。ガンダルフを光が包む。
メリーとピピンの2人は森の住人エントの保護下に入り、中つ国でもっとも安全な場所で守られている。ガンダルフはアラゴルンたちを連れてエドラスへ行きを提案した。
サルマンが結成した魔の軍勢は手始めとしてローハンの制圧を目論んでいる。ローハンが落とされると人間の勢力は衰退著しいゴンドールを残すだけになってしまう。それを阻止するためにローハンを死守する必要があった。
そんな場所を抜けてようやく黒門の前へと到着する。だが黒門はオークたちの厳重な見張りで一分の隙もなかった。黒門が通行不能とわかると、ゴラムは実は秘密の道があると告げる。
サムは反対したがフロドはゴラムを信用して南へと進路を改める。
その途上で、オリファントを連れた南方人の軍団を目撃する。しばらく見ていたフロドたちだったが、突然何者かが南方人たちを襲った。ファラミアを中心とする要撃隊だった。
フロドとサムは戦闘の中心から逃れようとしたが、ファラミアにスパイと疑われ、捕まってしまう。ファラミアはボロミアの兄で、オスギリアスを守る戦士であった。ファラミアはフロドが力の指輪を持っていると知ると、その身柄を拘束しゴンドールへと連れて帰ろうとした。
物語の舞台はラウロスの大瀑布を抜けてローハン草原へと入っていく。そこから先は人間達の住処である。第1部におけるよう
もはや小人が楽しい冒険を歌にして歌ったり、魔法のアイテムが絶体絶命の危機を救ってくれたりもしない。そこは「望みを失った」土地であるのだ。
剣を振り回しての戦いばかりではない。エドラスの黄金館へ行くとサルマンの放ったスパイがセオデン王を悪の道へと唆そうとしている。旅の仲間たちは力だけでなく智恵も勇気も、その資質を極限まで試されようとしているのだ。
第2部において特筆すべきは飛躍的に進歩したデジタル技術で
ゴラムの技術は文句なしの喝采を浴びてその年のアカデミー賞をもたらし、技術的問題を理由に凍結していた多くの映画の企画を再スタートさせた。ゴラムの影響は想像以上に大きく、映画の歴史を一歩前進させたのだ。
これが活用されたのはウルク=ハイの軍勢だ。ウルク=ハイは訓練されたスタントに数時間かかるメイキャップを施し、鍛冶職
そうするとどう考えても人数的限界に直面する。メイキャップアーティストだけでも数百人が映画制作に参加していたが、それ
黄金館はスカンジナビアの伝承『ベーオウルフ』からほぼそのまま採用されている。『指輪物語』は多くの神話、伝承を元素に描かれている。特に『古エッダー』からの影響は大きく、ガンダルフや『ホビットの冒険』の登場人物の名前はほぼここから引用されている。
ローハンを舞台にした戦いの1つ1つは容赦のない迫力だ。甲冑を泥だらけにして血にまみれ、犠牲者を出しながらなおも戦い続ける。我々が目撃しているのはまさに歴史上の英傑たちの戦いなのだと思わせられる。
だが誰一人として引き返そうとしなかった。彼らは暗黒の狂気に
いや違う。彼らは信じていた。この深い闇を抜けたそこに光が輝く瞬間があると。それは古里のためであり、そこで待つ子供たちのためであり、その背に世界の全てが背負わされている。
だから戦士達はどんなに傷つこうとも、側で仲間たちが倒れようとも、前に進むのを止めようとしない。自らの使命を知っているから。
目指す場所はこの世で最も暗く、醜い魔物が巣をつくり、冥界が口を開いて待っている場所だ。冥王のいるそこは地獄へと繋がっている。そんな恐怖を知りつつも、戦士達は決して引き返そうとしない。
望みを失ったこの世に、望みが失われた瞬間に。できるのはただ一つ、信じるだけ。希望を失わず耐えるだけ。命を懸けて戦うに足りる、尊い世界のために。
小さな望みはもっとも小さな者たちに託されて、使命は必ず果たされると信じ、戦士たちの旅はまだ続く。
第1章『旅の仲間』を読む
第3章『王の帰還』を読む
映画記事一覧
作品データ
監督:ピーター・ジャクソン 原作:J・R・R・トールキン
脚本:フラン・ウォルシュ フィリパ・ボウエン
コンセプチュアルデザイナー:アラン・リー ジョン・ハウ
音楽:ハワード・ショア 主題歌:エミリアナ・トリーニ
撮影:アンドリュー・レスニー 編集:ジョン・ギリバート
衣裳:ナイラ・ディクソン リチャード・テイラー
出演:イライジャ・ウッド イアン・マッケラン
〇 ヴィゴ・モーテンセン ショーン・アスティン
〇 ビリー・ボイド ドミニク・モナハン
〇 オーランド・ブルーム ジョン・リス=デイヴィス
〇 ショーン・ビーン アンディ・サーキス
〇 ケイト・ブランシェット リヴ・タイラー
〇 マートン・ソーカス イアン・ホルム
〇 バーナード・ヒル ミランダ・オットー
〇 カール・アーバン デヴィッド・ウェンハム
〇 ブラッド・ドゥーリフ クリストファー・リー


